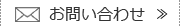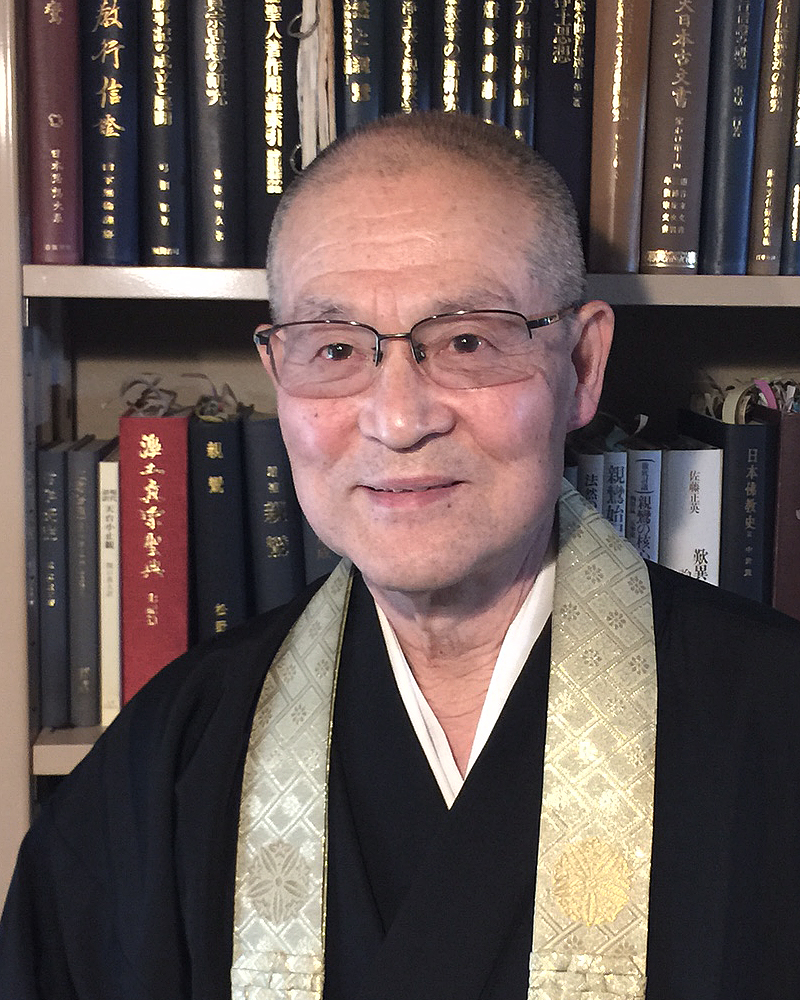壇ノ浦において建礼門院が入水した真相〔論文〕/研究論文アーカイブスの詳細ページ/浄土宗西山深草派 宗学会
※発言はFacebookアカウントにて行なってください。
[登録カテゴリー: 歴史学]
【筆者】 吉良 潤 (きら じゅん)
はじめに
角田文衛氏は論文「安徳天皇の入水」(『古代文化』二十七巻9号1975年所収)において、下のように論じられた。
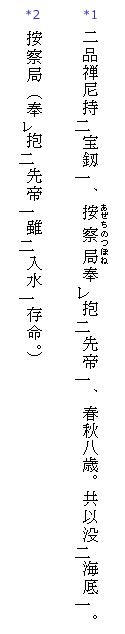
一、
日本の歴史を通じて元暦二年(1185)三月における安徳天皇の入水ほどいたいたしい、悲愴な事件は稀である。 言ふまでもなくそれは、三月廿四日―陽暦では五月二日―の午後遅くのことであった。
通説では、安徳天皇の外祖母の二位尼こと従二位・平時子が天皇を抱いて御座船から飛び込み、海底に沈んだことゝなっている。 (中略)それゆゑ、『平家物語』の諸本や『源平盛衰記』(巻第四十三)に見受けられる右の入水に関する叙述は、修飾的な部分はともかく、骨格的な筋書きの方は、それ自体ではあながち否定されないのである。 問題は、二位尼が果たして天皇を擁して海に沈んだかどうかにある(傍線筆者)。 と言ふのは、この入水に関しては通説とは違ふ然も有力な所伝があるからである。
二、
これもよく知られてゐることであるが、『吾妻鏡(あづまかがみ)』には、叙上の通説とは異なった所伝が載せられてゐる。 即ち、その元暦二年(文治元年)三月廿四日条には、(*1) と記されている。 つまり二位尼は神釼を奉持しただけであり、天皇を抱いて沈んだのは、按察局であったと言ふのである(傍線筆者)。 更に同書によると、四月十一日、義経が飛脚に託した壇浦の海戦の報告書『一巻記』が頼朝の手元に届いた。 義経の軍陣にあった祐筆の中原信(のぶ)泰(やす)が執筆したこの『一巻記』の重要部分は、『吾妻鏡』の同日条に掲載されている。 そこには、入水した後に救助された按察局について、次のやうに記載されてゐる。 (*2)
つまり『吾妻鏡』の所伝では、天皇を抱いて入水したのは按察局の方であって、二位尼は神釼のみを奉持して海に沈んだことになっている。 『一巻記』は、義経が提出した報告書であるだけに、この所伝も無碍に却(しりぞ)け難いのである。
奇妙なことに、この按察局の名は、かくも重要な役割を演じたと伝へられるにもかゝはらず、『平家物語』や『源平盛衰記』には全く見出されない。 しかし『吾妻鏡』に明記されている以上、実在の女性であったことは確実である。 当時の記録をあれこれ渉猟してみると、『按察』と言ふ名を持つ女房は、二人見出される。 一人は、高倉天皇の内裏女房の按察典侍であって、天皇に寵されて治承三年(1179)に皇女(後の潔子内親王)を産んだ女性である。 この女房は平家とは余り関係がなく、天皇の崩後は都にあって皇女を育てゝゐたやうであるから、壇浦の按察局とは別人と認めて差支へがなからう。
もう一人は権大納言按察使・藤原公通(きんみち)(1117~1173)の娘で、皇太后(のち建春門院)・平滋子に仕へてゐた按察局である。 嘉応元(1169)年二月十三日、皇太后・滋子が日吉神社に行啓した日、彼女は唐衣(からころも)を着、皇太后と同輿している。 彼女は皇太后と同輿したのであるから、よほど側近に仕へる上﨟の女房であったに相違ない。
この按察局は、一条局とも呼ばれることがあったらしく、『建春門院中納言日記』(第六段)には、次のような記載が見られる。 一条殿(按察の大納言きんみちのむすめ。 頭中将(実宗)ひとつ腹。 せうと、車よせなどして、もてなして参らせられたり。 )彼女が『一条』と呼ばれたのは、彼女の里第が外祖母―上西門院の乳母の一条局―の一条室町第(一条大路北・室町末路西)であったためであろう。
皇太后滋子の日吉神社行啓があってから、二年十箇月たった承安元年(1171)の十二月に、平徳子は入内して女御とされた。 徳子は翌年二月早くも中宮に冊立されたが、この際建春門院から多数の女房が中宮の方へ転属したことが知られてゐる。 尤もその中には、安元二年(1176)七月、建春門院が崩じた後に転じた女房もゐたであらう。 その時期はともかくとして、按察局が建春門院から中宮・徳子の方へ移ったことは、充分に想定される。 彼女は建春門院の『番の女房たち』の中では第二位を占める女房であった。 従って中宮(=建礼門院)の方においても、彼女は御匣殿内侍(みくしげどのないし)のやうな地位を持つ最上﨟の女房であったに相違ない。
言ふまでもないが、寿永二年(1183)七月、平家一門が西奔した時、建礼門院の女房で女院と行を共にしたのは、平家とよほど関係の深い人達ばかりであった。 すなはち、『吉記』の寿永二年(1183)七月廿五日条には、「主上(安徳)御乗車、御乳母二人、并按察局、御乳人一人(遠江) 釼璽等御同車、...」とあり、安徳天皇が都を後にされた時、按察局は天皇と同車するほど重要かつ密接な地位にあったことが知られる。
のみならず、壇浦で海に身を投じた女房、と言ふよりも女性たちは、平家や安徳天皇と切っても切れない関係を持つ者に限られてゐた。 その中でも按察局は、天皇を抱いて入水したと『吾妻鏡』に伝えられるほど平家と緊密な関係を持ち、かつ最重要な地位を占めてゐた。 それは彼女が平家の中でも有力な立場にある誰かの妻であったからである。
(中略)
按察局が勇猛さをもって知られた能登の守・教経らの母であったかどうかは不明である。 しかし上西門院と係はりが強かったことや、入水の際に重要な役割を演じたことから推しても、彼女が一門の長老たる教盛の妻であったことは、ほゞ確かであらう。 女性の身で決然として入水した彼女には、教盛の妻としての強烈かつ悲壮な覚悟があったものと想察される。
角田文衛氏は誰が安徳天皇を抱いて入水したのかという問題に就いて、左のように述べられた。
結局、慈円や行長ないし時長などが置かれていた環境に想ひをめぐらしてみると、二位尼が安徳天皇を抱きかゝへて入水したと言ふ『愚管抄』や『平家物語』の叙述は真実を伝へていると認めざるをえない。 四月十一日に鎌倉に届いた義経の『一巻記』は、四月三日、義経から後白河法皇に呈された書札と同様、まだ戦塵の収まらぬ三月廿五日にあはただしく起草されたものであり、そこに調査不充分な箇所が若干あったとしても、当然のことであった。 御座船に乗ってゐた女性たちはまだ気持ちが動顛してをり、男性もまだ極度の興奮状態にあり、詳しい情況を尋ねることは出来なかったはずである。 敵を殲滅した以上、義経は相手の情況を急いで調べる必要はなかった。 それどころか、彼は神剣を捜し出す手配、負傷者の手当や戦死者の調査、葬送などに忙殺されてゐたであらう。 『一巻記』の内容に少々の誤りがあるのは、止むを得なかったのである。 たゞこの『一巻記』に按察局の名が録されてゐるのは、史料として頗る貴重とさるべきである。 (62ページ)
角田文衛氏は上記のように考えられた。 しかしこの考察は大部分が憶測と推定に基づいている。 だから筆者も同じように憶測と推定でもって、下記のように考えるのである。 すなわち、
寿永二年(1183)義経は源範頼とともに頼朝の代官として出陣し、元暦二年(1184)京中に狼藉を繰り返していた源義仲を討ち、摂津一谷(いちのたに)の平家軍を破って、海上に追い払った。
その後、都の治安を担当したが、頼朝の許可を受けずに後白河上皇から検非違使(けびいし)・左衛門少尉(さえもんのしょうじょう)に任じられ、頼朝が警戒するようになって、平家追討の任を解かれた。 しかし頼朝は義経の軍事的才能に頼らざるを得ず、文治元年(1185)再び義経に平氏追討を命じた。 義経は二月、讃岐国屋島に陣を構えていた平氏を奇襲し、三月、壇ノ浦で平家を壊滅した。 この間、作戦に関して義経の監視役であった梶原景時と対立した。 従って義経は頼朝に戦況の報告をするときに、細心の注意を払ったはずである。 安徳天皇の入水には多くの鎌倉武士が関与し、また注視していたから、間違った報告は梶原景時とその部下により摘発され頼朝に讒言されることは明らかであった。
義経は祐筆・中原信泰の報告書『一巻記』等をしっかり検分してから頼朝に送ったと思われる。 従って安徳天皇入水の一件に関する限り、『吾妻鏡』に載せられた記事こそが一次史料であって、『平家物語』その他の資料は二次史料と断定してよいと考えるのである。 すなわち、按察局は安徳天皇を抱いて入水し、天皇を海水中に残して独り鎌倉武士に引き上げられたのであった。
角田文衞氏の「憶測と推定」に対抗して、筆者は上のような「憶測と推定」を提示することができるのである。
本 論
角田文衛氏は綿密な研究によって、按察局(あぜちのつぼね)が『平家物語』の諸本に見出されないけれども、『吾妻鏡』、『吉記』、源義経から源頼朝へ報告書『一巻記』によって実在の人物であった事を明らかにされ、さらに按察局が平教盛の妻であったことを発掘された。 そこで、筆者は角田氏が採用されなかった史料によって、角田氏の研究を補強し、さらに何故、按察局は『平家物語』の諸本に記されていないのか、その事情を明らかにしたい。
方法論
一次的史料だけを用いて研究を進める。 次の史料を一次的史料と考える。
Ⅰ 『吾妻鏡』に引用された『一巻記』の内容
Ⅱ『遣迎院阿弥陀如来像胎内文書』の「結縁交名」
Ⅲ『吉記』
Ⅰ
文治元年(1185)三月二十四日、
(前略)午の刻になって平氏方がついに敗戦に傾くと、二品禅尼(平時子)は宝剣を持ち、按察局は八歳の先帝(安徳)抱き奉り、ともに海底に没し容た。 藤の重(かさね)の御衣を着た建礼門院(徳子)が、入水されたところを、渡部党の源五馬允(うまのじよう)が熊手で引き上げ奉った。 按察局も同じく生き残った。 ただし、先帝はついに浮かび上がられなかった。 (後略)
文治元年四月小十一日、
(前略)
廷尉(源義経)が一巻の記録を進めてきた。 中原信泰(信康)がこの記録を書いたという。 これは、先月二十四日、長門国赤間関の海上に八百四十余艘の軍船を仕立て、平氏もまた五百余艘を漕ぎ出して合戦し、午の刻に逆賊の平家は敗北したことについてである。
一、先帝(安徳)は、海底に沈まれました。
一、入海した人々
二位尼上(平時子)
(中略)
一、若宮(守貞王)建礼門院(平徳子)は無事にお救い申し上げました。
(中略)
女房
帥典侍〔先帝(安徳)の御乳母(めのと)〕 大納言典侍(平輔子)〔(平)重衡卿の妻〕
帥局(そちのつぼね)〔二品(平時子)の妹〕
按察使局(あぜちのつぼね)〔先帝を抱き奉って入水したものの生存〕
(以下略)
すなわち、按察局は文治元年(1185)の壇ノ浦決戦において安徳天皇を抱いて海に飛び込んだけれども、海の中で思わず安徳天皇を手放してしまった。 そして頼朝側の武士によって海から引き上げられたのである(『一巻記』)。
Ⅱ
遣迎院阿弥陀如来像の胎内文書の「結縁交名」(青木淳氏著『遣迎院阿弥陀如来像像内納入品資料』)の中に按察局の名が見出される。 それは(④1)の5行目、上から4段目の「尼按察殿」である。 遣迎院交名は建久五年(1194)に成立したと考えられる。 建礼門院徳子に仕えた「按察局」が出家して法然の『師秀説草』を聴聞し、結縁喜捨した。 そして交名帖に「尼(あま)按察殿(あぜちどの)」と書き入れられたと思われる。
すなわち彼女は壇ノ浦の悲劇から九年後、都において法然が行った逆修説法(1194)を聴聞し、法然の信者になっていたことになる。 『逆修説法』と『遣迎院阿弥陀如来像胎内文書』の「結縁交名」が共に建久五年(1194)に成立したものであることは、別の論文で論じる。
Ⅲ
『吉記』の寿永二年七月二五日条(『新訂吉記』本文編三、髙橋秀樹編、和泉書院90ページ)から抜粋延書した。
これを見ると、按察局は安徳天皇と上級の乳母二人、そしてもう一人の遠江という乳母と同車した。 安徳天皇の母・建礼門院と祖母の平時子は別の車に乗った。 抱かれなければならない幼い天皇を母后が抱くことはないのである。 長時間の行幸に際してそうであったし、また宮中での儀式においても、幼帝は若くて逞しく身分の高い乳母に抱かれるのが常であった。 この時代の公家の日記類を見ると同様の情景が記されている。
従って安徳天皇を海の底の都に連れて行くときも変わりはないのである。 二位の尼・平時子は宝剣を腰に差して真っ先に入水した。 続いて按察局が安徳天皇を抱いて飛び込んだ。 建礼門院は二位の尼から、生き残って入水した天皇と平家一門の菩提を弔うように命じられていたが、安徳天皇の後を追って海に飛び込んだ。 そして義経が率いる関東の武士によって引き上げられたのである。 この情景は『吾妻鏡』の文治元年(1185)三月二十四日条に記されている。
上記のように、関東の武士たちが義経の右筆である中原信泰(信康)に証言している。 この平家壊滅の有様を頼朝に『一巻記』として文書で報告し、さらに後日、直接頼朝の幕営に参上して、頼朝の質問に答えた中原信泰はどういう人物であろうか。 すぐに思い当たるのは源頼朝の右筆になった中原広元(後の大江広元)である。 大江広元が頼朝と鎌倉幕府を支えた功績が大きいものであったことは論じるまでもない。
中原広元がいわゆる京下りの官人として鎌倉に下向したのは、寿永二年(1183)の末から元暦元年(1184)の初め頃であった。 義経が頼朝の命令によって、範頼とともに軍を率いて木曽義仲を攻めたのは寿永二年(1183)の冬であった。 そして元暦元年(1184)一月二十日、義仲は敗死した。 同日、義経は入京し、一月二七日、義仲追討を鎌倉に報告し、同二九日に範頼とともに、平家追討のために西に向かった。 二月七日、早くも一の谷の平家を破った。 そういう次第で、義経は鎌倉へ報告するために右筆が必要となった。
一方、頼朝に仕えた中原広元は元暦元年(1184)頼朝の右筆として活動を始め、三月頃、後白河院への奏状を執筆した。 すなわち中原信泰と中原広元は同時期に清和源氏の両雄の右筆となったのである。 目崎徳衛氏が論文「鎌倉幕府草創期の吏僚について」(『三浦古文化』第一五号)で指摘されたように、頼朝の吏僚に中原氏が多かった。 中原信泰もその一人と考えられる。 中原信泰はその出身と役職柄、冷静に戦の結末を観察し、正確に記録することに専念したと考えられる。
以上の論考から、『吾妻鏡』に抜粋された『一巻記』の内容と『吾妻鏡』の文治元年(1185)三月二十四日条の記述は歴史的事実としてよいであろう。
最後に角田文衞氏が疑問とされた問題に答えたい。
按察局は、安徳天皇を海底に残して自分が生きて都に帰ったことを深く慚愧したと思われる。 特に建礼門院には、合わせる面目がなかったはずである。 按察局を迎えた都の人々は、彼女の心情を忖度して慰め、あるいは沈黙したと推定される。 この問題は平家物語の成立問題に関わってくる。 筆者は次の論考「建礼門院が往生した時と場所」において「原平家物語の成立問題」と絡めて究明する予定である。
結 論
- 二位の尼・平時子は宝剣を持して壇ノ浦に入水した。
- 按察局は安徳天皇を抱いて入水したが、天皇を水中に残して自分一人引き上げられた。
- 我が子・安徳天皇を追いかけて海に飛び込んだ建礼門院も、義経の部下によって引き上げられて死ぬことができなかった。
【発言や反論について】
- この論文・記事への発言や反論等は下のFacebookコメント欄にて行なってください。
- ご発言・ご反論はどなたでも自由に行なっていただけますが、投稿前に必ず発言・反論ルールをご参照頂き、ルールに則ったご発言をお願いいたします。
- 投稿公開の判断は中立的な立場で行ないますが、ルールを無視したものや公序良俗に反するものは公開を見合わせて頂く場合がございますので予めご了承下さい。
(非公開の場合でもFacebookの仕様に則り投稿者とその友達にはそのまま表示されます。) - 非公開となりましたご発言やご反論には、その旨の連絡や返信は致しません。こちらも併せて予めご了承下さい。
関連・類似した論文や記事 (12件)
facebook area